
今回紹介する1冊はこちら。
『ドイツはなぜ日本を抜き「世界3位」になれたのか』
【著 者】・・・熊谷 徹
【発行日】・・・2024年9月10日
【頁 数】・・・174ページ
Contents
著者はどんな人?
- 1959年東京生まれ。
- 早稲田大学政経学部卒業後、NHKに入局しワシントン支局で米ソ首脳会談などを取材。
- 90年からはフリージャーナリストとしてドイツ・ミュンヘン市に在住。
本書の特徴
国際通貨基金(IMF)は2024年4月21日に公表した世界経済見通し(WEO)の中で「2023年のドイツの名目GDPが、55年ぶりに日本を抜いて世界第3位になった」と明らかにしました。
本書は「”GDP逆転”納得の理由」として様々な要因を上げています。
首相シュレーダー氏の改革『アジェンダ2010』
1990年代後半に「欧州の病人」とまで呼ばれたドイツが急激な発展を遂げた第一の要因は、1998年から2005年まで首相を務めたゲアハルト・シュレーダー氏が断行した「シュレーダー改革」にあります。
これは「国からの給付を減らし、国民の自己責任と自助努力を促進することにより国家の建て直しを計る」という提案です。
ドイツは社会保障制度が手厚い国なので賃金以外の労働費用が高く、人件費の高さが成長の足枷となり企業収益を圧迫し、企業の国際競争力が弱まっていました。
企業や個人が負担する社会保険料が多い反面、ケガや病気で失業した場合の保障も十分だと言えます。
しかし、働いて給料から税金や社会保険料を支払うよりも、長期失業者になって国から援助金を受け取った方が手取りが多くなるケースが現れました。
シュレーダー政権は、長期失業者への援助金、生活保護の額を減らし、給付条件を大幅に厳しくした。公的健康保険のカバー範囲を狭くしたり、患者の自己負担額を増やしたりすることで保険料の伸び率を抑えました。
シュレーダー氏は「国は困窮者には手は差し伸べるが、市民も自助努力を増やしてほしい」と国民に要求しました。
ドイツと中国の貿易増加
ドイツの製造業は自動車、機械製造、化学を中心として中国に大きく依存しており、中国は8年連続でドイツにとって最大の貿易パートナーでした。
ドイツの財の輸出額が21世紀に大きく伸びた一因は中国貿易の増加とのこと。やはり人口の多い大きな市場にアクセスできるということは重要。
ユーロ導入による為替リスクの消滅とドイツのインフレ
21世紀にドイツの名目GDPが伸びた背景として、ユーロ導入を始めとするEUの市場統合、政治統合の効果も無視することはできない。
ユーロの導入によりユーロ圏の市場にアクセスし易くなり、為替リスクも消滅。
名目GDPは「実際に取引される価格水準を基準としてドル建てで推計」する指標なので、日本のように円安ドル高になれば名目GDPは低くなります。
そしてドイツの2023年の物価上昇率は日本の1.8倍とのこと。物価が上昇すれば財やサービスの合計であるGDPも上昇します。
効率よく働いて結果を生もうとするのはドイツ人の国民性
1時間当たりの労働生産性がドイツに大きく水をあけられている理由として著者は以下のように分析しています。
ドイツ人の労働時間は日本人よりも約17%短いのに、労働により生み出す価値は日本よりも約43%多い。
政府が法律によって労働時間や休暇日数を順守するよう定めていることに加え、労働組合の影響力が強いことも関係している。
ドイツでは「仕事の成果を生むためにかける時間は短ければ短いほどよい」と考えるとのこと。
実はドイツ経済は落ち込んでいる
2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、スタグフレーションに襲われ深刻な景気後退に苦しんでいるとのこと。
ドイツ在住の著者も「名目GDPで日本を抜いたというニュースを一瞬信じられなかった」と述べています。
ドイツが抱えている課題として、ウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰、最大の貿易パートナーである中国経済の後退、労働人口の減少、スタグフレーション・・・。
ブルームバーグのドイツ版ニュースサイトは2023年11月27日、「ドイツが世界第3位になったのはこの国が成長したからではない。日本が沈んだのだ。」と悲観的な論評を発表した。
本書でこのように紹介されているように、今回のGDP逆転については決して喜ばしいことではないとのこと。
読んで感じたこと

本書はドイツの経済史をざっくりと学ぶことができ、現在におけるドイツと日本の経済的立ち位置を把握することができる本です。
- ドイツがどのような経済を歩んできたのか
- 働き方や社会保障などドイツのお国柄
- 日本の盛衰の理由
など、ドイツ在住のジャーナリストである著者だからこそ感じることのできる「ドイツの現状」がリアルな文章で書かれているだけでなく、しっかりとデータが示してあり、説得力のある内容となっております。
国の経済は自国内だけでなく、他国や時勢などさまざまな要因が複雑に絡み合って形成されるため、思いもしない事柄が影響を与えることもあります。
本書は現代におけるドイツ経済にスポットを当てた本となっておりますが、これをきっかけに世界経済へ目を向けていくこともできます。
現代人が持つべき経済の知識として必要であると感じました。
本書のポイント
本書が伝えたいこと
- シュレーダー改革により企業の国際競争力を強化
- 労働時間が短いのは国の政策と国民性
- 実はドイツ経済は落ち込んでいる
- ドイツと日本が持つ経済の課題について
関連書籍
関連書籍の紹介記事もあるので、ぜひご覧ください!

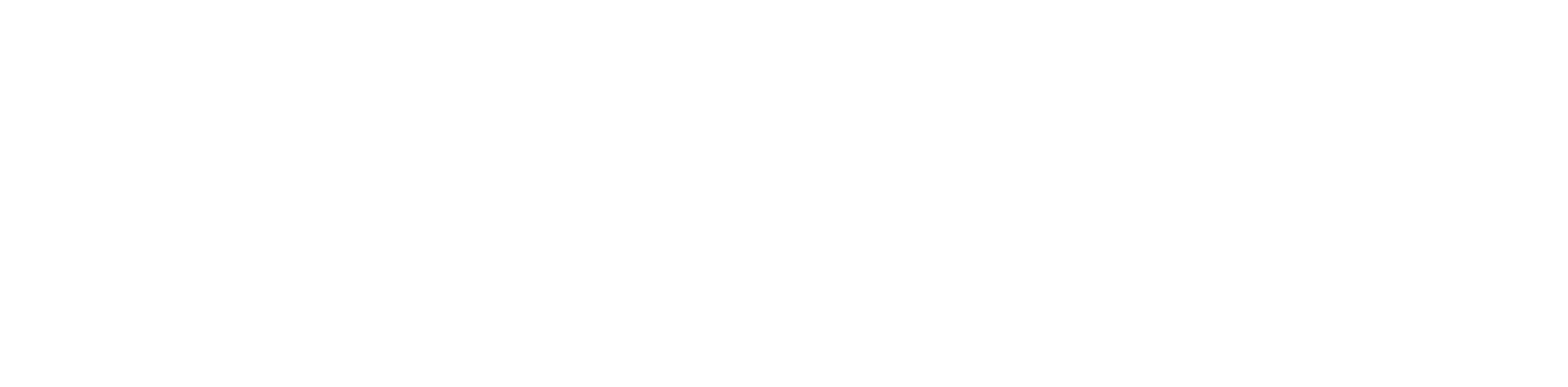
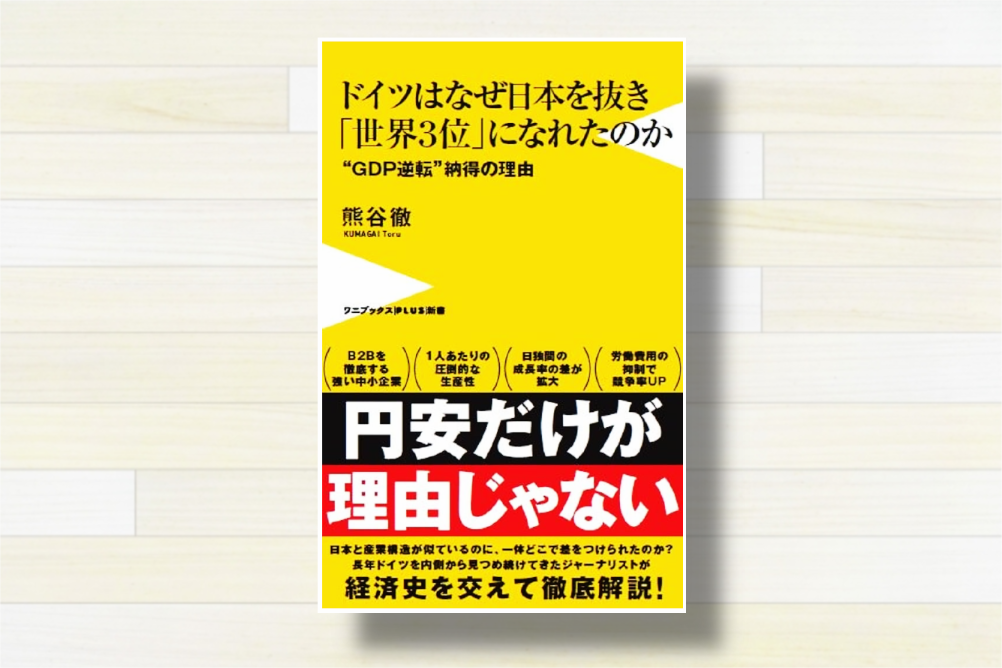

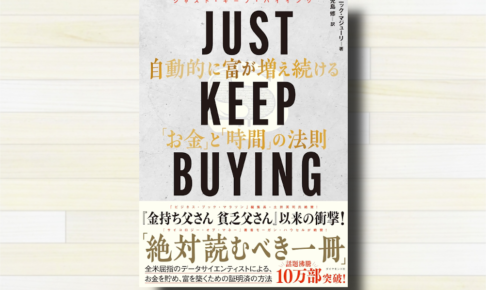
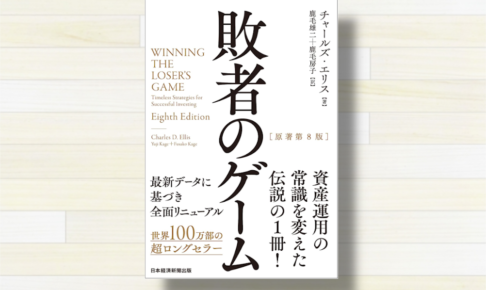
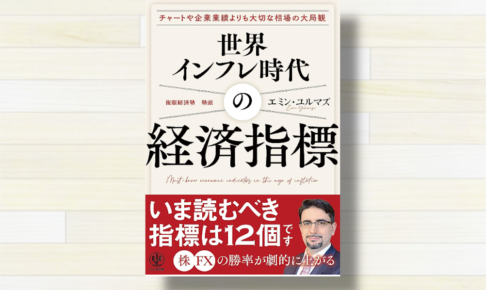




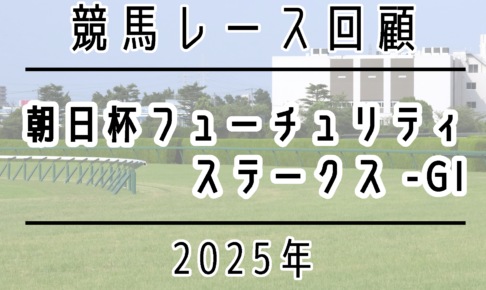
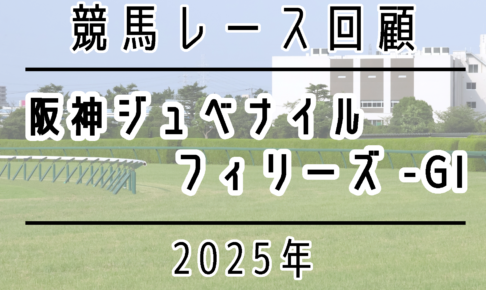
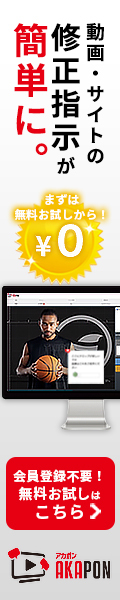
ブログ「としけば!」にようこそ!